そばは元々、「蕎麦がき(かいもち)」として食べられていました。
端的に言えば、そば粉を餅状にしたものです。
蕎麦の歴史は相当古く、奈良時代より前からあった事は確実でしょう。
一説には9000年以上前からあったそうです、中国4000年の歴史なんて目じゃないですね。
蕎麦の育成は比較的容易で、かつ成長が早く、痩せた土地でもしっかりと実をつけたため、非常食的にも日本全国に広まっていました。
転機を迎えるのは江戸時代よりちょっと前。
蕎麦がきだと一気に食べられない事から、細くしたところ格段に食べやすくなりました。
しかし、十割そばはボロボロになり、つながらないので難しい…。
そこで「つなぎ」という文化が地方独自に産まれます。
小麦を入れて、つなげる事はわかっていたのですが、当時の小麦はたいへん高価なもの。
なので、地域で色々なつなぎが生まれました。
例えば、新潟のへぎそば。
つなぎに布海苔を使います。
また、山間部などでは、長芋ですね。
昨今のとろろそばは上にかかっているものが多いですが、その頃はそばの中にも入っていました。
そうすることで、そばはより細く、よりコシが強く、よりおいしくなり、爆発的に広まることになります。
江戸時代にはそばは現在の形になっており、つゆは醤油がまだ出回っていなかったので味噌で作った「たれみそ」と大根のしぼり汁を付けて食べていました。
江戸時代中期には、そばは細く長いので長寿の縁起物とされたり、年越しそば、引っ越しそばなどの文化も定着。
町にはそばの屋台が立ち並ぶほどになりました。
庶民的になり過ぎたため、落語などでも題材にされています。
そんな所から、当時のそばに対する向き合い方などを推し量ることができたりします。
江戸時代中期~末期になると江戸そばの代表として名高い「藪(やぶ)」「更科(さらしな)」「砂場(すなば)」の「のれん御三家」が出てきます。
いわゆる「江戸三大蕎麦」ですね。
と、まあ、とめどなく話が溢れてしまうので歴史はこれくらいにして…w
そんな江戸のソウルフード、そばの粋でいなせな美味しい食べ方をご紹介します。
にほんブログ村 グルメブログ そば・うどんへ
でも、粋な食べ方って…やっぱりあの落語の??
なんて、知っている人は知っているかと思いますが、そばをちょっとだけ付けて食べるスタイルは藪蕎麦発祥説が有力です。
藪蕎麦のつゆは、非常に塩辛いつゆだったので、むしろそういう食べ方だったんですね。
ただ、この食べ方は思ったより理に叶っていると思っています。
まず、そばというのは淡い香りなので簡単にそばつゆの香りに負けてしまいます。
ほんとに繊細なので、下手をするとそばの香りを感じない人もいます。
そばの香りが強い場合は、そばの香りが強い品種を手に入れているからですが、そばの香りが高い=良いそばではないのがポイントです。
食感、栽培の難しさ、のど越しなどの方が評価としては高く設定されているのがほとんどだそうです。
また、そば殻などを入れて挽く場合もあるそうです。
このやり方だとそばの香りは高くなりますが、その分そばの香り+雑味もプラスされるので、ここでもそばの香りが高い=良い蕎麦かというのは覆される感じですね。
ただ、そばの香りはとっても独特なので少しでも味わいたいですよね。
だから、このちょっとだけ付ける手法になります。
こうする事で噛んだ時に、そばの香りが口に広がりやすくなります。
もっとそばの香りを楽しみたいという方は、塩という手があります。
これはそばの甘味もより感じられるようになるので、おすすめです。
粋でいなせな蕎麦の食べ方
かけそばはもう全部どんぶりに入っているので、好きに食べてください。
もりそばについて解説してきたいと思います。
高級店でも立ち食いそば店でも楽しめる方法です。
今回はゆで太郎さんに行きました(ブログ的に当たり前ですが…)。
まずはもりそばを頼むと、そば、薬味、そばつゆが来ますよね。
そしたら、まずは何もつけずに、一口より少し少なめにそばを取って、すすりましょう。

そして、よく噛む。
これでそばの香りを楽しむことができます。
ゆで太郎さんは、そば粉を55%使用している稀有なそば屋さんなので香りをつかむ事も容易かと思います。
そしたら、今度も同じように一口少なめを取って…

1/4だけ、そばつゆにつけます。
ほんとにちょっとだけで大丈夫です。

こんな感じに。
そして、一気にすすります。
すすらずに噛みながら、食べるのはNGです。
口の中に香りが広がらないからです。
そばはすすった方がそばの香りも、つゆの香りも口の中に広がります。
そして、軽く噛んでください。
さっきより塩っ気を感じて、弱いそばつゆの香りを感じられると思います。
それだけやったらもう大丈夫。
ここまでが粋な食べ方です。
あとはいなせな食べ方で、残りを食べましょう。
ドボンと付けるもよし、薬味を乗せて食べるのもよしです。
ゆで太郎さんは、半つけを推奨しています。
それゆえに、少しそばつゆは濃い目です。
薬味の扱い方についても少し…。
薬味はそばつゆに入れるより、そばに直接乗せた方がそばもそばつゆも薬味も損ないません。
大体、ネギやわさび、一味唐辛子などがついてきたり、置いてあったりしますよね。

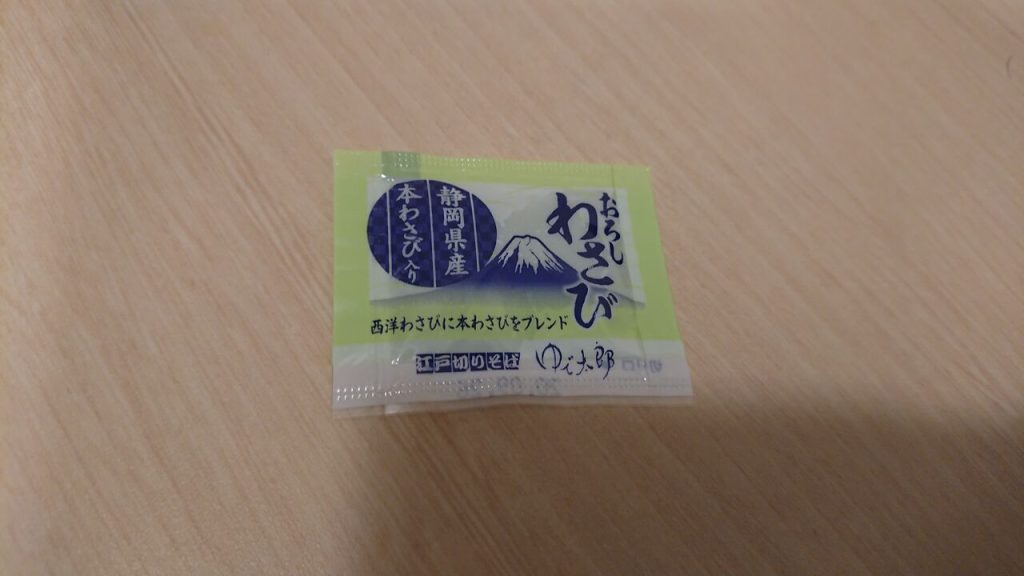
自分の好きなのをチョイスして、そばに直接乗せましょう。


これを下からつまんで食べるのが美味しいです。
わさびは、そばに伸ばした方がいいですね。
一度、試しにこれで食べてみてください。
そば、そばつゆ、わさび、ねぎを全て感じられます。
そして、最後にそば湯ですね。
薬味の時に、そばの上に乗せて食べたら、わさびなどがそばつゆに溶かし過ぎなくなります。
そうすることで、よりそば湯とそばつゆの味を堪能できます。
是非、お試しくださいね!!



コメント